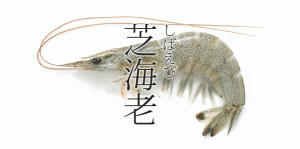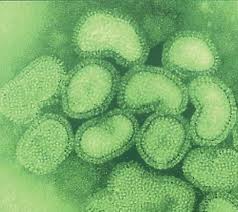10月20日 日曜日 しとしと雨
休日当番日にて院内におります。きょうは近傍の医療センターが電気系統の点検のための停電にて、救急当番の責任重大の一日なのです。いつもお世話になってばかりなので、こういう時はしっかりとやらねば・・・。終わってみればやはりやや忙しい一日でした。クリニックで初めて救急車の受け入れもあり、何となく新鮮な日となりました。大きな事故などがなくてよかったと、胸をなでおろしております。もっとも今や丹後半島ではドクターヘリも飛んでおりますので、直接3次救急へのアクセスも可能となり、とりまく状況は格段に良くなっているわけなのではありますけれど。
また明日からは新しい1週間を頑張る事にしましょう。
休憩時間にはスタッフと秋の実りを頂きました。

放送のテレビのコメンテイターが仰っていました。日本はいまや世界中から注目される国のひとつなのだそうな。何せ2020年のオリンピック開催、他国でもあまり例のない大胆な金融緩和政策、福島の汚染水の今後などなど・・・消費税の上乗せ分は社会保障政策の実現に使うと聞いているのですけど、最近漏れ伝えてくるニュースは介護保険や公費補助の負担部分のアップのお話ばかりのような気がするのは私だけでしょうか?一方では新国立競技場には数千億円の予算が投入されようとしているとか。う〜ん、被災地復興の事も考えると本当にバランスのとれた予算組みなのかな〜と思ってしまいます。ま、何はともあれ国会議員さんたちには、より多くの人たちが納得できる政策を実現して頂くようにお願いしたいものですね。