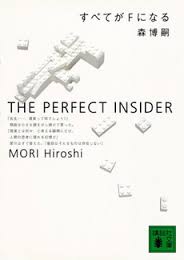11月18日 月曜日
更新を怠りながらも月日の流れは早いものです・・・。メニュー誤表示事件であれやこれやと書き綴りましたので一寸休憩しておりまして申し訳ございません。今日もそれほどネタはありませんので先週末からのできごとをニュースフラッシュ的に羅列しておきます。
◯ 勤務していた病院でお世話になった内科の先生の結婚式に出席・・・小生がプリンスとあだ名を付けていた先生だったのですが、そのニックネームどおりにプリンセスを射止めておられました。その時に着ていたスーツに虫食いがあったことを帰ってきてから発見してボー然。
◯ 新たに往診に伺うことになった患者さんとお出会いしました。これからよろしくどうぞ。ご家族や患者さんと話をして初めて色々なことに気付かされます(勤務医時代にはまったく想像もできなかったことなどもあり、まだまだだなあと・・)。
◯ 毎週往診に伺う先の方からいつも頂き物をするのですが・・・それがとっても暖かい感じで嬉しい・・・
◯ 息子が英語のチューターから頂いてきたCDに触発されて見た映画「グッドモーニングベトナム」傑作でした。音楽も抜群、ヒロイン(?)役の娘がかわいい!!ロビンウィリアムスの早口にも圧倒。iTune便利!!

◯ 週末はときどきに家族で訪れるこのお店・・・ベタな感じではありますが好きなのです。
◯ もう一つの週末は、いろいろと理由がありまして、名古屋日帰り往復を。名古屋って大阪の要素もあって、東京のニュアンスもある不思議な街ですねえ。味噌煮込みうどんの麺が硬いっ!!名物なのですけど変わってる。